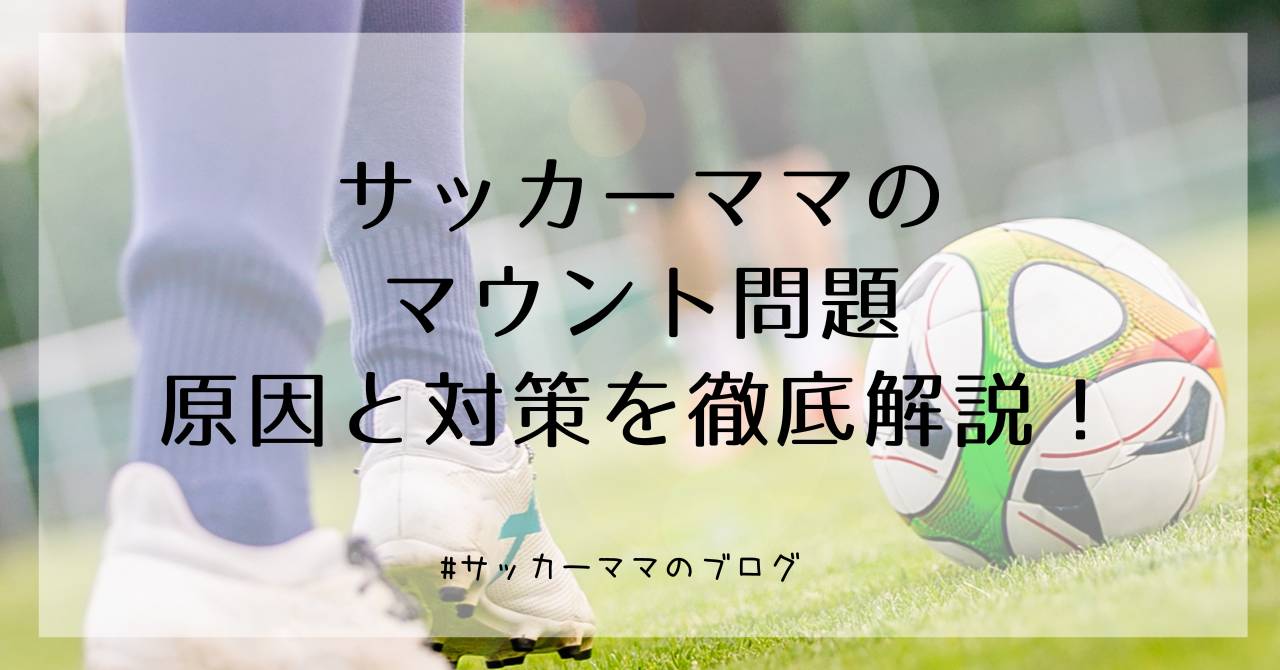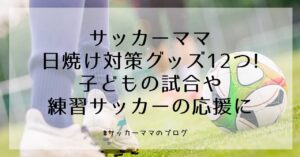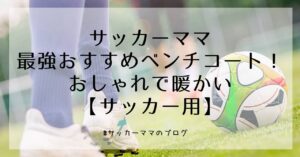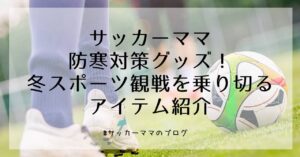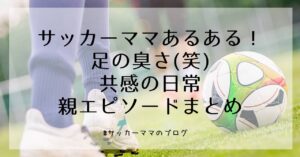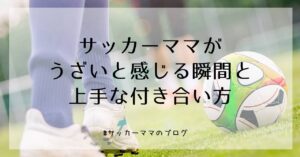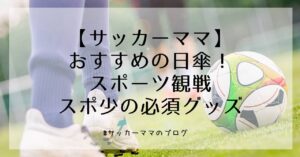こんにちは!7年目のサッカーママ、あっちです。
息子が小学1年生でサッカーを始めてから、早7年。
今では中学生になった息子を見守りながら、サッカーママ歴を重ねています。
みなさんの中にも、お子さんがサッカーを始めて、「わぁ、楽しい!」と思う反面、
「え?こんなに大変なの?」と驚いている方もいるのではないでしょうか。
特に気になるのが、サッカーママ同士の付き合い。
中でも最近よく耳にするのが「サッカーママのマウント」問題。
「うちの子、この前の大会で3点決めたの♪」 「え〜すごい!うちの子なんて…」
こんな会話、聞いたことありませんか?
今回は、そんなサッカーママのマウント問題について、原因と対策を徹底解説します!
この記事でわかること
- サッカーママのマウントの実態
- サッカーママのマウントが起こる原因
- サッカーママからマウントされたときの対処法
- 健全なサッカーママコミュニティを作るためのヒント
サッカーママのマウントの実態
まずは、サッカーママの世界でよく見られるマウントの実態を見ていきましょう。
1. 子どものサッカーの実力に関するマウント
「うちの子、トレセン合格したの〜」
「え〜すごい!うちはまだ…」
子どものサッカーの実力や所属チームの成績を自慢するママたち。
時には露骨に、時には謙遜しながら遠回しに自慢してきます。
例えば、「うちの子、最近全然ダメで…」と言いながら、実は先週の試合で決勝ゴールを決めたことをさりげなく伝えるなんてこともあります。
また、他の子と比較して「○○くんはすごいわね。うちの子なんて足元にも及ばないわ」と言いつつ、実は自分の子の方が実力があると思っていたりするケースも。
このような言動は、聞いている側のママたちに不快感や劣等感を与えてしまう可能性があります。
2. 経済力や社会的地位を背景にしたマウント
「この前の遠征、パパが仕事で忙しくて私が運転して行ったの。新しい車、乗りやすくて助かったわ〜」
高価なブランド品や高級車、夫の職業など、さりげなく経済力や社会的地位をアピールするママたちもいます。
例えば、「うちは共働きだから大変で…」と言いながら、実は夫が大手企業の役員であることをほのめかしたり、「子どものためなら何でも揃えてあげたいけど、予算と相談しながらね」と言いつつ、最新の高価なスパイクを買い与えたりするケースも。
また、遠征や合宿の際に、わざわざ高級ホテルに宿泊したり、豪華な差し入れを用意したりして、さりげなく経済力をアピールすることもあります。
このような行動は、経済的に余裕のない家庭のママたちに対して、プレッシャーや疎外感を与えてしまうかもしれません。
3. 親の教育方針や子どもへの関心の高さに関するマウント
「毎日練習に付き添って、ビデオも撮ってるの。子どものためなら時間も労力も惜しまないわ」
熱心に子どもの練習に付き添ったり、試合の応援に駆けつけたりすることで、「良い母親」をアピールするママたちも。
例えば、「仕事を調整して、毎日送り迎えしているの。大変だけど、子どものためだから」と、自己犠牲的な姿勢を強調したり、
「うちは家族ぐるみでサッカーに取り組んでいるの。休日は家族全員で練習に付き合ってるのよ」と、家族の協力体制をアピールしたりすることも。
また、「子どもの将来のために、今のうちからプロ選手を目指して特別なトレーニングも始めたの」と、過度な教育熱心さを示すケースもあります。
このような言動は、仕事や他の家庭の事情で十分に時間を割けないママたちに対して、罪悪感や不安を抱かせてしまう可能性があります。
マウントが起こる原因
なぜ、サッカーママの間でマウントが起こるのでしょうか?
主な原因を見ていきましょう。
1. 承認欲求の強さ
実は、マウントをする人の多くは自信がない人たち。
子どもの実績や自分の努力をアピールすることで、周りから認められたいという気持ちが強いのです。
これは、自分自身の価値を子どもの成功と結びつけてしまっている場合が多いです。
例えば、自分の仕事や生活に満足していない場合、子どもの成功を通じて自己実現を図ろうとすることがあります。また、自分の子育てに自信がない場合、他のママたちから「素晴らしい母親だ」と認められることで、その不安を埋めようとするかもしれません。このような心理は、無意識のうちにマウント行為につながってしまうのです。
2. 競争意識の高さ
サッカーは競技スポーツ。子どもたちの競争が、そのまま親同士の競争に発展してしまうことも。
特に、トレセンや強豪チームへの所属、試合での活躍など、目に見える形で子どもの実力が評価される場面が多いサッカーでは、親同士の競争意識も高まりやすいのです。
「うちの子が一番」という思いが強くなると、他の子やその親を下に見たり、自分の子を過大評価したりする傾向が出てきます。
また、「負けたくない」という気持ちから、他のママたちの言動に過敏に反応し、自分も負けじとマウントしてしまうこともあります。このような競争意識は、健全なコミュニティ作りの障害となってしまう可能性があります。
3. 価値観の押し付け
「サッカーで成功 = 人生の成功」と考えるママもいます。
自分の価値観を他の人に押し付けようとする傾向が、マウントにつながることも。
例えば、「サッカーに全てを捧げるべき」「プロを目指すなら今からこれをすべき」といった考えを、絶対的な正解のように主張するケースがあります。
また、「サッカーで成功すれば、将来は安泰」「サッカーで培った精神力は、どんな場面でも役立つ」といった考えを、まるで事実のように語ることも。このような価値観の押し付けは、サッカーに対する取り組み方や考え方が異なるママたちを不安にさせたり、プレッシャーを与えたりしてしまう可能性があります。
4. コミュニティへの帰属意識
「みんなと同じでなければ」という思いから、周りに合わせようとするあまり、マウントに走ってしまうケースも。
サッカーチームという小さなコミュニティの中で、「浮いてしまいたくない」「仲間外れにされたくない」という気持ちが強くなると、周りのママたちの言動に過剰に同調してしまうことがあります。
例えば、本当は毎日の送迎が大変だと感じていても、「子どものためなら何でもする」という雰囲気に流されて、無理をしてしまうケース。
または、高価な用具やユニフォームの購入、遠征への参加など、経済的な負担を感じながらも、「みんなやっているから」と無理をしてしまうこともあります。このような同調圧力は、結果的にマウント合戦を助長してしまう可能性があります。
5. 情報過多による比較
SNSなどで他の家庭の様子を知る機会が増え、必要以上に比較してしまうことも原因の一つです。
InstagramやFacebookなどのSNSで、他のママたちが子どもの活躍や家族の様子を投稿しているのを見ると、つい自分の状況と比べてしまいがちです。
「あの子はこんなに活躍しているのに、うちの子は…」「あの家族は毎週末サッカーを楽しんでいるのに、うちは…」といった具合に、SNS上の情報と自分の現実を比較し、焦りや不安を感じてしまうのです。
そして、その焦りや不安が、実際の対面でのマウント行為につながってしまうことがあります。また、SNS上でも「いいね」やコメントの数を気にするあまり、過度に自慢げな投稿をしてしまい、それが他のママたちへのマウントになってしまうケースもあります。
マウントされたときの対処法
では、実際にマウントされたとき、どう対応すればいいのでしょうか?
1. 深呼吸して、冷静になる
まずは、深呼吸。相手の言動に対して感情的にならないよう、落ち着きましょう。
マウントされると、つい腹が立ったり、落ち込んだりしてしまいますよね。でも、そんなときこそ冷静さが大切です。「1、2、3…」と心の中で数を数えながら深呼吸をしてみましょう。感情をコントロールすることで、相手の言動に振り回されずに済みます。また、その場で反応せずに、後で冷静に考える時間を作ることも有効です。「そうなんだ」とさらっと受け流し、家に帰ってから自分の気持ちと向き合うのもいいでしょう。
2. 相手の気持ちを理解する
マウントする人は、実は自信がなかったり、不安を抱えていたりします。相手の気持ちを想像してみましょう。例えば、「子どもの成績を自慢する人は、実は子育てに不安を感じているのかもしれない」「経済力をアピールする人は、他の面で自信がないのかもしれない」といった具合に、相手の言動の背景にある気持ちを考えてみるのです。このように相手の立場に立って考えることで、マウントに対する反感や嫌悪感が和らぐかもしれません。さらに、相手に共感を示すことで、マウントの連鎖を断ち切ることもできるでしょう。
3. 自分の価値観を大切にする
他人と比べる必要はありません。自分の家庭の価値観を大切にし、自信を持ちましょう。「うちの子は○○ができていない」と焦ったり、「あの家庭のように△△すべきだ」と思い込んだりする必要はありません。例えば、「うちの子はサッカーを楽しんでいるから、それでいい」「家族の時間を大切にしているから、毎日の送迎は無理しない」といった具合に、自分たちの価値観を再確認してみましょう。また、子どもの成長は人それぞれ。今はできなくても、将来伸びる可能性は十分にあります。長い目で見守る姿勢が大切です。
4. さらっと流す
「そうなんだ〜」とさらっと流すのも一つの手。深入りしないことで、マウントの連鎖を防げます。例えば、「うちの子、トレセン合格したの〜」と言われたら、「そうなんだ、すごいね!」と素直に褒めた後、「そういえば、次の試合の集合時間って何時だっけ?」と話題を変えるのもいいでしょう。または、「へぇ、そうなんだ。うちの子も頑張ってるよ」と、相手の話を受け止めつつも、自分の子どもの話にさらっと切り替える方法も。このように、相手の言葉に乗らず、かといって無視もせず、適度な反応を返すことで、マウントの効果を薄めることができます。
5. 必要なら距離を置く
どうしても付き合いづらい人とは、適度な距離を保つのも大切です。全ての人と仲良くなる必要はありません。マウントが多い人や、一緒にいると気分が落ち込む人とは、少し距離を置いても構いません。例えば、そういう人がいる集まりには参加頻度を減らしたり、会話の時間を短くしたりするなどの工夫をしてみましょう。また、他のママたちと仲良くなることで、マウントする人との接触を自然と減らすこともできます。ただし、完全に避けるのではなく、最低限の礼儀は保ちましょう。チームの和を乱さないよう、バランスを取ることが大切です。
健全なサッカーママコミュニティを作るためのヒント
最後に、みんなが楽しくサッカーを応援できる環境づくりのヒントをお伝えします。
1. 子どもの気持ちを第一に考える
勝敗や成績よりも、子どもが楽しんでいるかどうかを大切にしましょう。時には「サッカー、楽しい?」と子どもに直接聞いてみるのもいいですね。子どもが「楽しい!」と答えてくれたら、それが何よりの成功です。逆に、「つまらない」「辛い」といった答えが返ってきたら、その理由を丁寧に聞き取り、対策を考えましょう。また、試合の後は「勝てた?」ではなく「楽しかった?」「どんなプレーができた?」と聞くことで、子どもの内面的な成長にも目を向けることができます。子どもの気持ちを第一に考えることで、自然とマウントも減っていくはずです。
2. 互いの頑張りを認め合う
他の子の頑張りも一緒に喜べる関係性が理想的です。例えば、試合で他の子が活躍したら「○○くん、すごいシュートだったね!」と素直に褒めましょう。自分の子どもにも「あのプレー、かっこよかったね」と言って、他の子の良いところを認める姿勢を見せるのもいいですね。また、練習中の頑張りや、試合でのチームワークなど、結果だけでなくプロセスも評価する視点を持ちましょう。「今日の練習、みんな本当に頑張ってたね」「負けちゃったけど、最後まで諦めずに走り続けてて感動したよ」といった言葉かけが、チーム全体の雰囲気を良くします。
3. 多様性を尊重する
サッカーとの関わり方は人それぞれ。互いの違いを認め合える環境づくりを心がけましょう。例えば、毎日練習に付き添えるママもいれば、仕事で週末しか参加できないママもいます。どちらが正しいというわけではありません。「うちはこうだけど、○○家はああなんだね。それぞれの形があっていいね」という柔軟な考え方を持ちましょう。また、子どもの目標も様々です。プロを目指す子もいれば、楽しむことが目的の子もいるでしょう。それぞれの目標を尊重し、応援し合える関係性を築くことが大切です。多様性を認め合うことで、マウントの少ない、健全なコミュニティができあがります。
4. コミュニケーションを大切にする
困ったことがあれば、率直に話し合える関係性を築きましょう。例えば、送迎や当番の負担が大きいと感じたら、「みんなはどう思ってる?もし大変だと感じている人がいたら、一緒に改善策を考えられたらいいな」と、オープンに話題を提起してみるのもいいでしょう。また、定期的に保護者会を開いて、互いの思いや悩みを共有する機会を設けるのも効果的です。その際、「批判はNG」「相手の立場に立って考える」といったルールを設けると、より建設的な話し合いができます。コミュニケーションを大切にすることで、マウントではなく、互いに支え合える関係性が築けるはずです。
5. 自分自身も楽しむ
子どものサッカーを通じて、ママ自身も新しい経験や出会いを楽しみましょう。例えば、他のママたちと一緒に応援グッズを作ったり、遠征先の観光を楽しんだりするのもいいですね。「子どものため」だけでなく「自分のため」の時間も大切にすることで、心にゆとりが生まれ、マウントとは無縁の楽しいサッカーママ生活が送れるはずです。また、サッカーを通じて学んだことを自分の仕事や生活に活かしてみるのも面白いかもしれません。チームワークの大切さや、目標に向かって努力することの素晴らしさなど、サッカーから学べることはたくさんあります。
まとめ
いかがでしたか?
サッカーママのマウント問題、実は多くのママが経験し、悩んでいる問題なんです。
でも、ちょっとした心がけと工夫で、みんなが楽しくサッカーを応援できる環境は作れるはず。
- マウントの背景にある気持ちを理解する
- 自分の価値観を大切にする
- 子どもの気持ちを第一に考える
- 互いの違いを尊重し合う
- コミュニケーションを大切にする
これらのポイントを意識しながら、子どもたちの成長を見守っていきましょう。
何より大切なのは、子どもたちが楽しくサッカーをしている姿を見守ること。
ママたちも、サッカーを通じて新しい出会いや経験を楽しみましょう!
子どもたちの成長と一緒に、私たちママも成長できるはず。
さぁ、今日も元気に「がんばれ〜!」って心の中で声をかけに行きましょう!