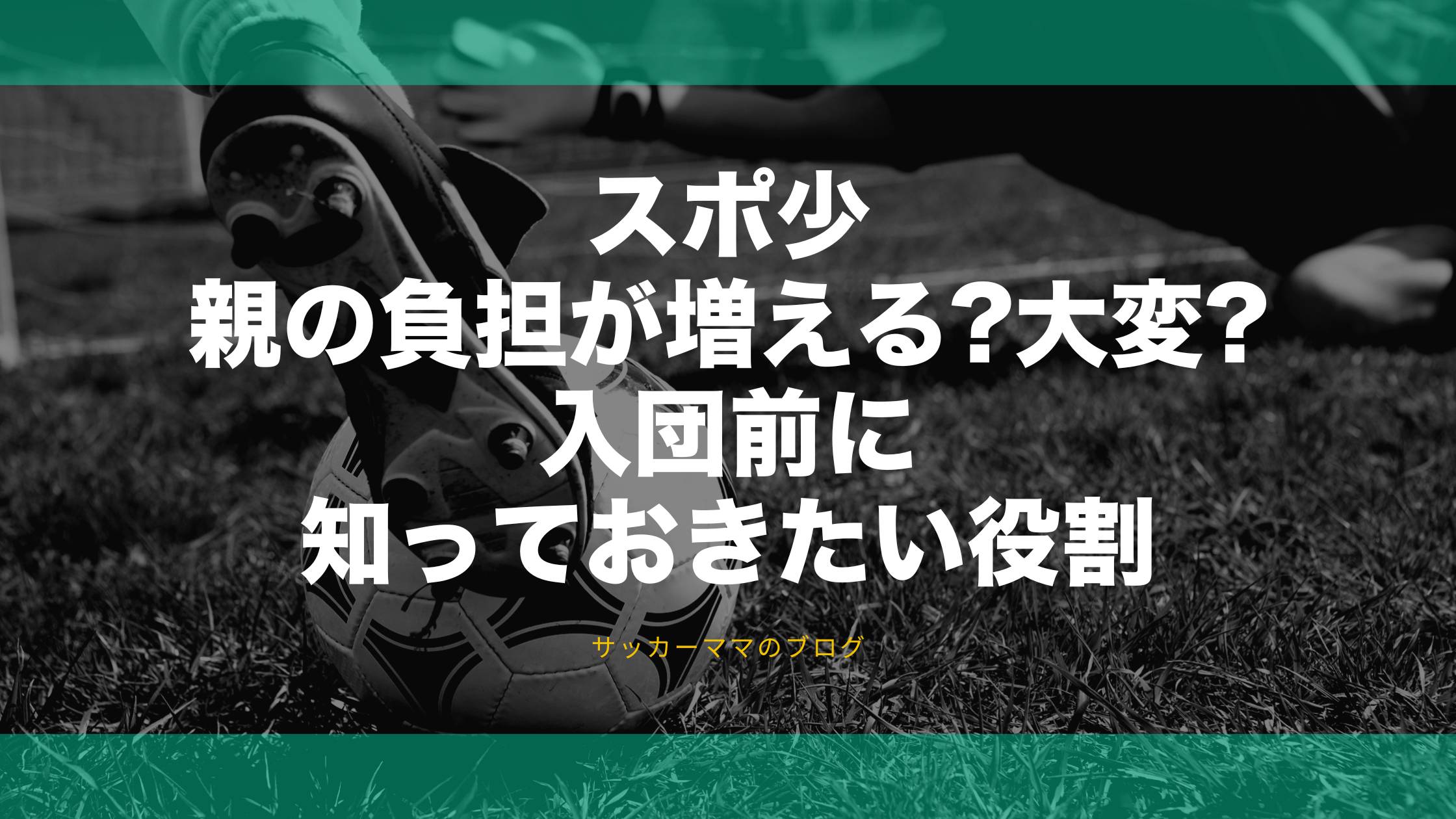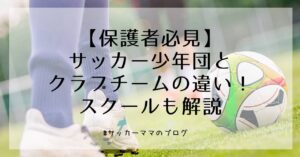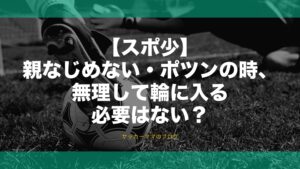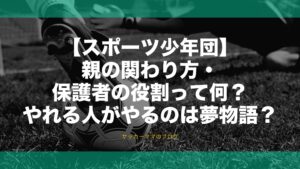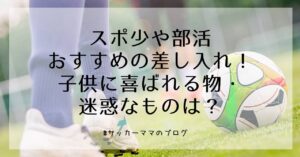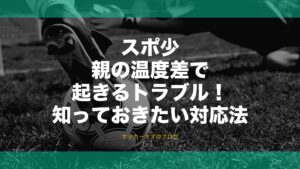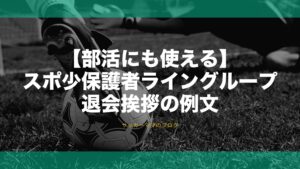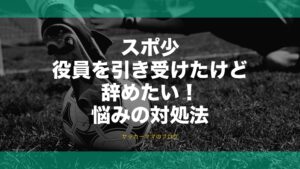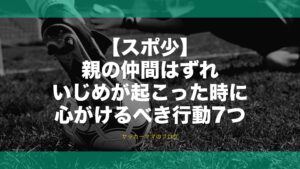こんにちは!7年目のサッカーママ、あっちです。
長男は小学生時代にのスポ少サッカー少年団のチームに6年間入団していました。
当時はスポ少生活を見守りながら、日々奮闘していました!
学校行事とかでママたちが集まると、必ずと言ってよいほど話題にのぼるのは「子どもの習い事」のことのことです。
私もだし、ママ友さんからもですが、
「〇〇ちゃん、何か習い事やってるの?習ってどう?」
などなど、お互いに情報交換をして、根掘り葉掘り聞いてしまいます。笑
そんな中「スポーツ少年団」で、運動をさせようと習い事として検討している親・保護者さんもいます。
みなさんの中にも、「子どもをスポ少に入れようかな」と考えているけど、
「入団したいけど、思った以上に親の負担が大変なのでは..」
「入団してみたけど、思っているよりスポ少は親の負担が多い..」
と感じている方もいるのではないでしょうか?
今回は、そんなスポ少にまつわる親の負担について、同じような思いをしてる方の参考になればいいなと思い、経験者の視点からお伝えしていきます。
この記事でわかること
- スポ少における親の役割と負担の実態
- スポ少の親の負担が増える理由
- スポ少の親の負担を軽減するためのコツ
- スポ少に入団するメリット・デメリット
- スポ少選びのポイント
スポ少は親の負担が大きい・大変と感じたこと
さて、まずはスポ少で親に求められる役割と、その負担の実態を見ていきましょう。
1. 金銭的な負担
スポ少に入ると、意外とお金がかかるんです。
- 月謝(年会費)
- ユニフォーム代
- 練習着代
- 用具代(サッカーならスパイク、野球ならグローブなど)
- 施設利用料
- 遠征費
- 送迎にかかるガソリン代
- お茶・お弁当代
- 保険料
などなど…。種目やチームによって違いますが、年間10万円以上かかることも珍しくありません。
特に遠征が多いチームだと、交通費や宿泊費でグッとお財布が痛む場合も。うちの長男のサッカーチームは年に2回ほど遠征があるのですが、1回で3万円くらいかかります。けっこう大変です(´;ω;`)
また、子どもの成長に合わせて用具を買い替えたり、大会参加費を払ったりと、予想外の出費も結構あります。例えば、うちの次男は野球を始めてから半年で足のサイズが1センチ以上大きくなり、スパイクを買い替えることに。これが意外とお金がかかるんですよね。でも、子どもの成長を実感できる瞬間でもあるので、複雑な気分です(笑)
2. 時間的な負担
これが本当に大変なんです。特に土日は1日つぶれることも…。
- 練習や試合の付き添い
- 送迎
- お茶当番
- 練習の手伝い
平日も、仕事終わりに急いで送迎…なんてこともザラにあります。
私の場合、長男と次男の練習日が重なると、夫と手分けして送迎したり、ママ友と協力して送迎を分担したりしています。それでも、正直クタクタです(;´∀`)
特に大会シーズンになると、朝早くから夜遅くまで拘束されることも。先日の地区大会では、朝6時に家を出て、夜9時過ぎに帰宅。その間、炎天下の中での応援や審判のお手伝いなど、まるで自分が選手になったかのような疲労感でした。でも、子どもたちの真剣な表情や、試合後の達成感に満ちた笑顔を見ると、疲れも吹き飛ぶんですよね。
3. 精神的な負担
意外と見落としがちなのが、この精神的負担。
- 指導者や他の保護者とのコミュニケーション
- チーム運営への関与(役員など)
- 子どもの怪我や体調管理の心配
特に、保護者間のトラブルや、指導者との意見の相違なんかがあると、本当に心が疲れちゃいますよね。
例えば、うちの長男のチームでは、試合の出場機会をめぐって保護者同士の意見が対立したことがありました。「もっと平等に出場機会を」という意見と、「実力主義でいいのでは」という意見が衝突して、一時はチームの雰囲気が悪くなってしまったんです。結局、コーチを交えて話し合いを重ね、お互いの立場を理解し合うことで解決しましたが、こういった経験は本当に心労が絶えません。でも、これも子どもたちのためと思えば、乗り越えられるんですよね。
スポ少での親の負担が増える・大変な理由
なぜ、スポ少では親の負担が大変なのでしょうか?主な理由を見ていきましょう。
1. 従来型の運営体制が続いている
多くのスポ少では、昔ながらの「保護者が全面的にサポートする」という体制が続いています。でも、共働き家庭が増えた現代では、この体制がマッチしなくなってきているんです。
例えば、平日の練習に毎回付き添いが必要だったり、休日の試合で朝早くから夜遅くまで拘束されたりするのは、現代の家庭事情にはなかなか合いません。うちの場合、夫婦で協力して何とかやりくりしていますが、シングルマザーの友人は本当に大変そうです。子どもがスポーツを楽しむためには、この辺りの体制を見直す必要があるかもしれません。
2. 指導者不足
ボランティアで指導してくれる人が少ないため、指導以外の仕事が保護者に回ってくることも。
これって本当に深刻な問題なんです。特に、専門的な知識や経験が必要な種目では、適切な指導者を見つけるのが難しい。うちの次男の野球チームでは、元プロ選手のコーチがいるんですが、週1回しか来られないんです。その他の日は、経験者の保護者が指導を担当していて、その負担は相当なものだと聞きます。指導者の確保と育成は、スポ少の質を維持する上でも重要な課題だと思います。
3. チーム運営の効率化が進んでいない
いまだに紙の連絡網やアナログな会計処理をしているチームも。これが保護者の負担を増やす原因に。
デジタル化が進んでいる現代社会なのに、スポ少の世界はまだまだアナログなんです。例えば、うちの長男のチームでは最近までLINEでの連絡が禁止されていて、すべて電話連絡。急な予定変更があると、連絡係の保護者が一人ひとり電話をかけて回らないといけなかったんです。これって本当に大変で時間もかかる。やっと今年からLINEグループを作ることになりましたが、こういった効率化の遅れが保護者の負担を増やしている一因だと感じます。
4. 保護者の意識の差
「積極的に関わりたい派」と「できるだけ負担を減らしたい派」の温度差が、トラブルの元になることも。
これ、意外と難しい問題なんです。例えば、うちのチームには「子どものためなら何でもする!」というスーパー積極派のママがいて、その人が勝手に予定を決めちゃったりするんです。でも、共働きや小さい子がいる家庭は、そんなに時間が取れない。そうすると、「あの人は協力的じゃない」とか、逆に「あの人押し付けがましい」とか、お互いの不満が溜まっていく。結局、子どものためと思ってやっていることが、大人同士のトラブルに発展しちゃうんですよね。みんなの事情を理解し合うことが大切だと思います。
5. 金銭的な問題
十分な資金がないと、外部サービスの導入など、負担軽減の取り組みが難しくなります。
これ、本当に悩ましい問題です。例えば、専門のコーチを雇ったり、効率的な運営システムを導入したりすれば、保護者の負担は確実に減ります。でも、そうすると月謝が上がってしまう。うちの長男のチームでは、月謝を2000円値上げして外部コーチを雇う案が出たんですが、「それだけ払えない」という家庭もあって、結局見送りになりました。みんなが参加できる金額で、かつ質の高い活動を維持するのって、本当に難しいバランスだなと感じます。
スポ少での親の負担を軽減するためのコツ
でも、大丈夫!負担を軽減するコツはあります。
1. チーム選びが重要
入団前によく調べることが大切です。
- 保護者の役割分担はどうなっている?
- 負担軽減の取り組みはある?
- 練習頻度や時間はどれくらい?
など、事前にチェックしておきましょう。見学や体験入団を利用するのもおすすめです。
うちの次男が入った野球チームは、「週末練習1/4ルール」といって、土日のどちらかの半日だけ練習、というのを採用していました。これなら家族の時間も作りやすいですよね。
また、チームの雰囲気も大切なポイントです。例えば、うちの長男のチームを選んだ理由の一つは、見学に行ったときの保護者同士の雰囲気がよかったから。みんな和気あいあいとしていて、初めて行った私にも気さくに話しかけてくれたんです。こういった雰囲気のよさは、長く続ける上でとても重要だと思います。逆に、ピリピリした雰囲気や、過度に競争的な雰囲気のチームは避けた方がいいかもしれません。
2. 役割分担を明確に
「できること」「できないこと」をはっきり伝えましょう。
私の場合、平日の送迎は難しいけど、土日なら協力できる、と伝えています。すると、他のママたちと協力して、負担を分散できるんです。
具体的には、チーム内で「保護者の availability シート」みたいなものを作るのがおすすめです。うちのチームでは、Googleスプレッドシートを使って、各家庭がいつ協力できるかを共有しています。例えば、「平日は18時以降なら送迎可能」「土曜日は終日OK」「日曜日は午前中のみ」といった具合に。これを見ながら、みんなで協力して役割を分担しています。
また、自分の得意分野を活かせる役割を引き受けるのも良い方法です。例えば、私はウェブデザインの仕事をしているので、チームのウェブサイト管理を担当しています。こういった形で、それぞれの特技や経験を活かせる役割を見つけられると、負担感も減りますし、やりがいも感じられると思います。
3. コミュニケーションを大切に
指導者や他の保護者とよく話し合うことが大切です。
悩みや不安は、一人で抱え込まずに相談しましょう。意外と皆同じように感じていたりするものです。
例えば、うちのチームでは月1回の「おしゃべり会」を開いています。練習終了後に30分ほど、お茶を飲みながらざっくばらんに話す時間です。ここで「実は送迎が大変で…」とか「子どもがモチベーション下がってて心配」とか、普段言いづらいことも話せるんです。
すると、「うちも同じ!じゃあ送迎協力しあおう」とか「うちの子もそんな時期あったよ。こうしたら乗り越えられたよ」とか、みんなで解決策を考えられる。こういった機会があると、保護者同士の絆も深まりますし、チーム全体の雰囲気も良くなります。
また、コーチとのコミュニケーションも大切です。例えば、うちの長男が練習についていけずに悩んでいた時、コーチに相談したら個別指導の時間を作ってくれました。保護者と指導者が協力して子どもをサポートする、そんな関係性が作れると理想的ですね。
4. 子ども自身の自主性を育てる
これ、意外と効果的なんです!
うちの長男は、4年生になってから自分で荷物の準備をするようになりました。すると、私の負担がグッと減ったんです。
子どもの年齢に応じて、できることは任せていくのも良いですね。
スポ少のメリット・デメリット
ここまで負担の話ばかりしてきましたが、スポ少には素晴らしいメリットもたくさんあります!
メリット
- 体力向上と健康増進: 定期的な運動で、子どもの体力がぐんぐん伸びます。
- 協調性や礼儀作法を学べる: チームプレーを通じて、協調性が身につきます。また、先輩後輩関係や対戦相手への礼儀など、社会性も育ちます。
- 達成感や責任感を味わえる: 試合で勝つ喜びや負ける悔しさ、チームの一員としての責任感など、人生の糧になる経験がたくさんできます。
デメリット
- 親の負担が大きい: 今回お伝えしてきた通り、金銭的・時間的・精神的な負担があります。
- 子どもの自由時間が減る: 練習や試合で拘束される時間が多くなります。
- 怪我のリスク: スポーツなので、怪我のリスクは避けられません。
スポ少選びのポイント
最後に、スポ少選びのポイントをまとめておきます。
- 子どもの興味・適性を第一に: 親の都合よりも、子どものやりたい気持ちを大切に。
- 練習頻度・時間をチェック: 家族の生活リズムに合うかどうか確認。
- 指導方針を確認: 厳しい指導を好むか、楽しみ重視かなど、方針が合うかチェック。
- 保護者の役割を事前に把握: どんな役割があるか、負担の度合いを確認。
- 見学・体験入団を活用: 実際の雰囲気を感じることが大切。
まとめ
いかがでしたか?
スポ少、確かに親の負担は大変です。でも、子どもの成長を間近で見られる喜びは何物にも代えがたいものがあります。
大切なのは、事前によく調べ、自分たち家族に合ったチームを選ぶこと。そして、無理のない範囲で関わっていくことです。
「頑張りすぎない」「できる範囲で」を心掛けながら、子どもと一緒にスポ少生活を楽しんでいけたらいいですよね。
みなさんも、素敵なスポ少ライフを送れますように!