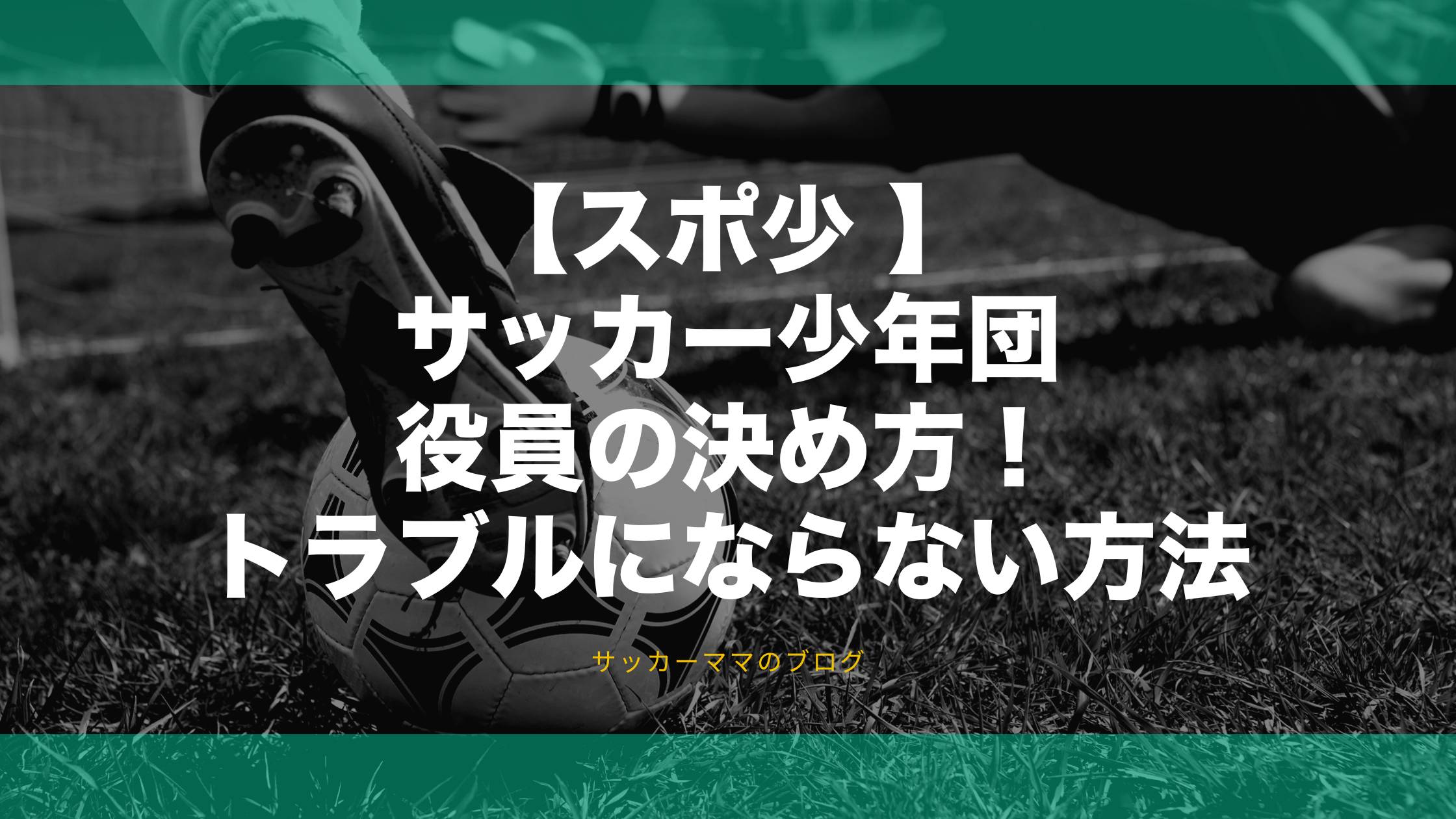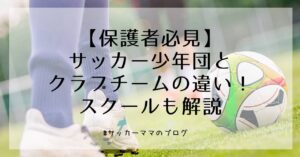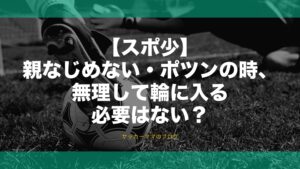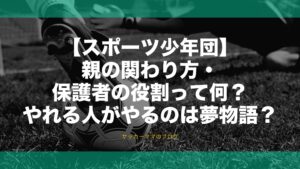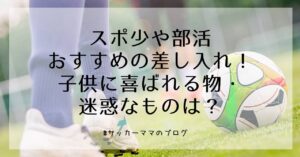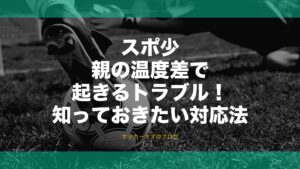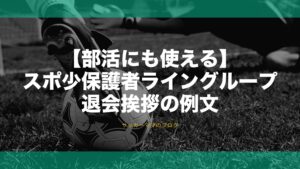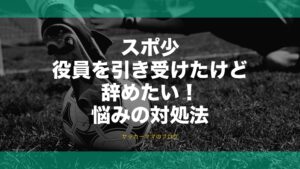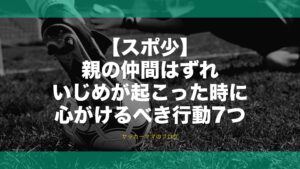みなさん、こんにちは。あっちです。
スポーツ少年団(スポ少)の役員決め、頭を悩ませていませんか?
実は、この役員決めが思わぬトラブルの原因になることも。
でも、大丈夫です。この記事では、スムーズな役員決めのコツをお伝えします。
スポ少の役員って、チームの運営に欠かせない存在です。でも、仕事量が多くて、正直大変。
だからこそ、役員を決める時にはみんなが納得できる方法が必要なんです。
「えっ、また私?」なんて言わなくて済むように、一緒に考えていきましょう。
スポ少役員の決め方と、それぞれのメリットとデメリット
スポ少役員の決め方①話し合いによる決定
話し合いで決めるのって、一見いい方法に思えますよね。
みんなの事情を考慮できるし、チームの現状にぴったりの人選ができます。
でも、注意点も。
時間がかかるし、人間関係が影響しちゃうこともあるんです。
「あの人、話が長いから嫌だな…」なんて思わないように、ルールを決めておくのがポイントかも。
スポ少役員の決め方②くじ引き(あみだくじを含む)
くじ引きって、公平感がありますよね。
感情的な対立も避けられるし、「運命」って感じで受け入れやすいかも。
私の経験では、保護者会長をあみだくじで決めることにしました。
なので、意外とスムーズに決まっちゃいました。
でも、「会計は経験者がいい」とか、適材適所で決めたい役職もあるから、全部をくじ引きにするのは難しいですね。
スポ少役員の決め方③立候補制
「やりたい人がやる」って、理想的ですよね。
意欲的な人が集まれば、チームも活気づきます。
でも、現実はなかなか厳しいかも。
「誰も手を挙げなかったらどうしよう…」って不安になることも。
立候補制を採用する場合は、役割の魅力をしっかりアピールすることが大切です。
スポ少役員の決めるトラブルを回避するための工夫
スポ少役員トラブルを回避①役割分担の明確化と透明性の確保
役員の仕事って、意外と「なんとなく」で進んでいることも多いんです。
でも、これが後々のトラブルの元に。
「言った、言わない」の水掛け論は避けたいですよね。
一番初めに、役割と仕事内容を明確にして、みんなで共有すること。
これ、めちゃくちゃ大切です。
LINEグループとかで情報共有するのも良いかも。
スポ少役員トラブルを回避②小さな協力から・多様な参加方法の設定
「役員は無理だけど、ちょっとならお手伝いできるよ」って人も多いはず。
そんな人のために、役職ではなく、何かを担当するサポーター制度を作るのはどうでしょう?
試合の日だけお茶出しを担当する、写真係になる、など。
小さな協力も、積み重なれば大きな力になります。
スポ少役員トラブルを回避③コミュニケーションの促進
役員決めで揉めるのって、結局のところコミュニケーション不足が原因だったりします。
定期的に懇親会やイベントを開催して、保護者同士が仲良くなれる機会を作るのが大切。
新入団の保護者向けのサポート体制を整えるのも良いですね。
「分からないことがあったら、いつでも聞いてね」って雰囲気があると、みんな安心します。
スポ少役員トラブルを回避④チーム全体での共通認識の形成
「うちの子をレギュラーにして!」なんて無理難題を言う保護者はどこにでもいます。
でも、そういう人が役員になったら大変ですよね。
だからこそ、チーム全体で「子供たちのため」という共通認識を持つことが大切。
保護者向けの意見交換会を開催して、みんなで同じ方向を向くことが大切です。
スポ少役員トラブルを回避⑤固定観念の払拭
中学の部活では、キャプテンの親が会長になるって聞きました。
でも、スポ少ではそれは難しいかも。
「レギュラーの子の親だから」「仕事が自由だから」って決めつけるのは避けたほうがいいですね。
チーム全体のバランスを考えて、みんなで協力し合える体制を作ることが大切です。
私の実体験:サッカー少年団チームでの役員決めした時
私のサッカー少年団チームでは、最高学年になるときに、団の運営・保護者会の会長などを決めるんですね。
話し合いで、
・過去に役職をやったとかは一度なし
・全家庭、保護者で決める
・みんなで協力して団の運営・保護者会をする
・会長は団をまとめる仕事、細かいことは他の役職の人がする
・会長はあみだくじにする
・他の役職は、まず会長を決めたあとに
ということで、保護者会の会長をあみだくじで決めました。
ちゃんと一人ひとり、線を追加もしましたよ。
その結果・・・・
私が会長を引いてしまったのです・・・!!!
正直、当たった時はびっくり!
でも、引いちゃったら「仕方ないかな」って思って、引き受けたのです。
他の役職は話し合いで決めましたが、、、
あみだくじで会長が決まったおかげで、みんな「自分も何かやらなきゃ」って思ってくれたので。
結果的に、スムーズに役員が決まりました。
【スポ少】サッカー少年団役員の決め方!トラブルにならない方法まとめ
結局のところ、大切なのは「公平性」「透明性」「参加のしやすさ」。
この3つを意識しながら、チームの実情に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。
多少役職によって負担は多くなったりしますが、
できるだけ仕事量が分散するようにすると「公平性」になります。
そのためには、何をやっていくのか「透明性」して
人によって不得意なことだとやりたくないので、得意なことをお願いすると「参加のしやすさ」に繋がります。
完璧な方法はないかもしれません。
でも、みんなで話し合って決めたルールなら、きっと受け入れやすいはず。
さて、皆さんのチームではどうやって役員を決めていますか?
うまくいっている方法、失敗した経験など、ぜひ教えてください。
みんなで知恵を出し合えば、きっといい方法が見つかるはずですよ。